適応障害”とは、
「ストレス因により引き起こされる情緒面や行動面の症状で、社会的機能が著しく障害されている状態」と “世界保健機構の診断ガイドライン” によって定義されています。
ストレスは、個人レベルのものから災害級の地域社会を巻き込むようなものだったり、また他人には何てことないことを過剰に感じてしまったりと受け方も人それぞれです。
つまり適応障害とは、ある生活の変化や出来事が本人にとってはすごく重大に感じてしまい、普段通りの生活を送るのも困難になったりすることです。
しかし、周囲より過剰に物事を感じることが悪いことなのでしょうか?
“感受性が高い” と捉え前向きに付き合っていくことはできないのでしょうか?
まずは “適応障害” にあらわれる様々な症状を見てみましょう。
「精神面」
●うつ状態
●不安
●緊張
●イライラ感
●焦り・緊張など
↑
実は本人よりも周囲の方々の方が気付くことの方が多いです。
本人は自分自身では何も状況が分からず、“周りが敵” くらいに感じることも少なくありません!
「身体面」
●多汗
●めまいなど
↑
原因不明の身体症状が出ることでまた焦りや不安、イライラが増幅します。
「行動面」
●暴飲暴食
●無断欠勤・欠席
●危険運転
●攻撃的姿勢・行動など
↑
“適応障害” という正しい認識をもっている方は少なく、残念ながら “性格の悪い人” と捉えられることも多いのが実情です。
冒頭で紹介しました “診断ガイドライン” によりますと、「発症は通常生活の変化やストレス性の出来事が生じて1カ月以内であり、ストレスが終結してから6カ月以上症状が持続することはない」とされていますが…
そもそもストレスが簡単に解消されるのであれば、精神科も心療内科も、我々心理カウンセラーも要らないんです!
それだけストレスとの向き合い方は大変難しく、センシティブに対応していかなければならないのです。
しかし世の中からストレスがなくなることは絶対にありえません。
コロナ禍でよく耳にする機会も増えた
“with コロナ” ですが、 “with ストレス” は地球上に生を受けている以上、動物でも植物でも人間でも等しくあるものです。
生きている以上、当たり前のことなのです。
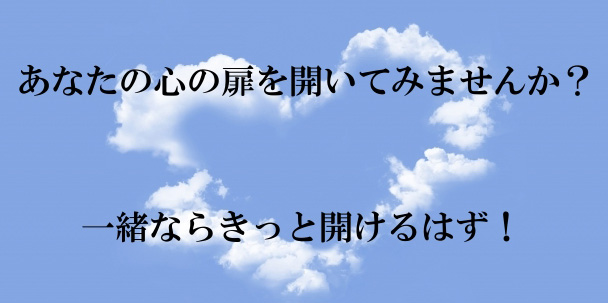
話しを “適応障害” に戻します。
適応障害…気を付けておきたいことがあります。
実際に適応障害と診断されてる方の40%の方が5年後にはうつ病などの診断名に変更されている事実があります。
統合失調症やうつ病などの診断基準を満たす場合はこちらの診断が優先されます。
適応障害よりも重い疾病という判断なのでしょう。>
ということは、適応障害を上手く解消・緩和できないと更なる精神疾患を引き起こすということです。
適応障害は重篤な病気の前段階である可能性があるともいえます。
では、どのように症状を改善すれば良いのか?
もちろん発症後、症状としてあらわれる部分に対しての薬物療法は必要です!
服薬し、落ち着いた精神状態でじっくりと置かれた状況を整理することは有効でしょう。
しかし、結局薬の効き目が切れた時に、落ち着いている時と同じ考え方・捉え方ができるかが問題です。
おそらく難しいでしょう。
まずはストレス因と離れる環境整備は必要になるかと思われます。
うつ病などとは違い適応障害の場合は、ストレス因と離れている間は落ち着くことが多いです。
例えば、職場のストレスが原因であれば、一度長期休暇などを得て距離を置くことも大事なことです。
そのうえでしっかりとしたカウンセリングを受け、精神面の調整方法などを学ぶことが効果的と考えます。
これも冒頭で述べましたが、出来事に対して周囲より敏感なのは “感受性が高い” という素敵なことでもあります。
一つの出来事でたくさんの考え方ができるということは、他の人にはできない “よりたくさんの人の考え方を理解できる能力” に他ならないと思います!
メンタルケアサロン心の翼 筑紫野二日市店では適応障害のデメリットの部分は緩和しつつも、メリットとして共に生きていくご提案をさせていただきます。
ご本人の良くなりたいという考えに自主性があれば、状況は絶対に好転します!
まずはご相談ください!